


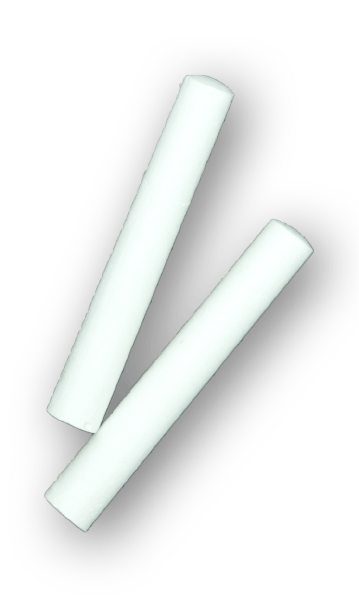

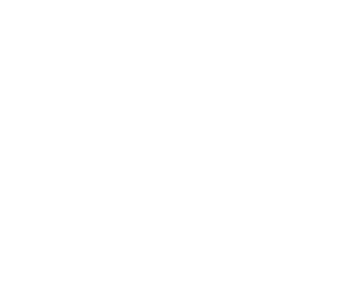

私は、島根県で小学校から高校までの学校生活を送り、中学校3年生の時の先生との出会いがきっかけで、教員を目指しました。通っていた学校は県内では規模の大きい学校でしたが、その先生は私に対して、褒めたり、アドバイスをくれたり、時には叱ってくれました。勉強自体が好きだったというわけではありませんが、その先生の授業は「一生懸命頑張ろう」と思わせてくれる先生でした。もともと地元で教員になりたいと思っていましたが、大学では一度県外へ出ました。そこで、改めて島根の良さを感じ、島根の教員を目指して勉強を始めました。大学在学中には、県外の学校や島根県の学校など様々な現場を見てきました。その中でも、やはり地元の子ども達のふるまいや地域に根付いた学習内容などは島根にしかないと思いました。現在勤務している学校でも、地域の特色を踏まえた学習を行っていますが、地域の方々がとても協力的で、子どもたちとの学びをとても楽しんでくださっているように感じます。そんな環境の中でふるさとのことを考えることができるのは、子どもたちにとっても自分にとっても、とても幸せなことだと思っています。

採用される前までは、「授業のうまい先生」「子どもに好かれる先生」になりたいと漠然と考えていましたが、採用されてからの学校生活の中で、自分が目指す教師像が少しずつ具体的になってきました。学校現場では、常に予定外のことが起きます。そのために準備することも必要ですが、そこで対応できなければ自然と子どもたちの学びの機会が奪われることになります。授業中でも「子どもの反応が自分の予想と違っていた・・・」なんてことは日常茶飯事で、その時に授業の本質をとらえることができる先生が「授業がうまい先生」といわれるのだなと感じ、これからも自己研鑽に努めようと思います。子どもたちは本当に先生のことをよく見ています。だからこそ、ここは譲れないという線引きを自分の中でしっかりと持って、子どもたちと関わっていきたいと思っています。線引きは先生によって変わりますが、甘いから好かれるというわけではなく、しっかりと筋が通っているから信頼される・好かれるのではないかと思っています。


仕事とプライベートを両立させるために、仕事を忘れて夢中になれる時間を作るようにしています。 大学在学中から始めたバスケットボールの指導に没頭している時間は、仕事のことを忘れて過ごしています。何かに熱中できる時間があるというのは、仕事とプライベートの線引きとして大切なのかなと思っています。また、毎日元気に過ごすためにしっかり休むというのも大切なことではないかと思います。健康的な生活リズムの基盤となる「早寝早起き」が最も疲れがとれるということに気づいたので、生活リズムを崩すことなく、オンとオフの時間を自分の中でしっかり作ることを大切にしています。
